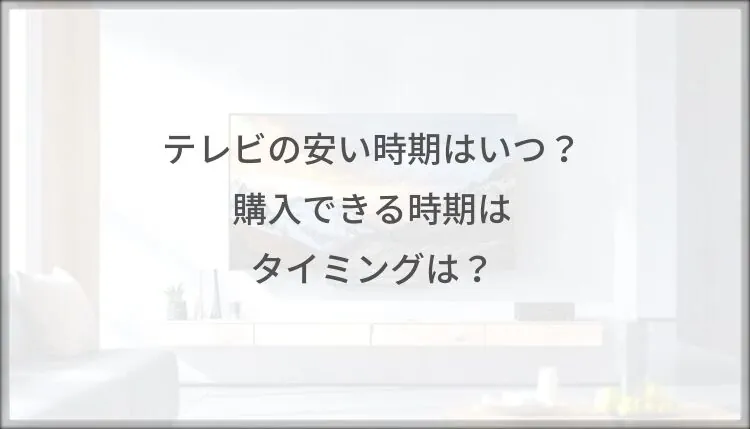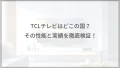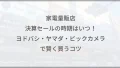この記事では、テレビをお得に購入できる時期について解説します。
新しいテレビを検討している方が特に気になるのは、テレビが一番安くなる時期ではないでしょうか?
実際、家電製品の価格は一定ではなく、変動が大きいです。セール時期や型落ちによって値段が下がることがよくあります。
テレビの買い替えタイミングに迷うことも多いですよね。購入してすぐに値下がりしてしまうことも珍しくありません。
この記事では、「テレビが安い時期」と「賢い購入方法」について詳しくご紹介します。
・安い時期にテレビを買い替えたい
・テレビをできるだけ安く購入したい
買い替えを検討している方は、ぜひ参考にしてお得にテレビを手に入れましょう!
テレビが最も安くなる時期
それでは、テレビが最も安くなる時期についてご紹介します。
家電量販店のセール時期が最もお得です。特にヤマダ電機やヨドバシカメラなどのセール時期を狙うのが賢明です。
主なセール時期は次の通りです。
・賞与支給時期(7月・12月)
・年末から新年にかけて
店舗によって若干の違いはありますが、上記の月にセールが行われることが多いです。セール時期は特に値引きが大きくなるため、このタイミングでの購入がおすすめです。
特に6~7月頃は最も価格が下がりやすい時期です。
これは、新製品が6~7月に発売されることが多いため、そのタイミングで型落ち品が値下がりするからです。
新製品の発売に合わせて、型落ちの製品を狙うとさらにお得に購入できます。
型落ち品とは、新製品ではない1世代前のモデルを指します。性能差はほとんどなく、新品で保証もついているため安心です。
最新モデルでなくても構わないという方には、型落ち品が断然お得です。
また、型落ちなど安く買いたいという方は「家電量販店の決算セール時期」を狙ってもいいのではと思えますね。
他にお得な時期は?
セール時期以外にも、テレビの価格が下がるタイミングがあります。それは、新製品が発売されてから3~4ヶ月後です。
この期間は売れ残りの在庫を処分するために、在庫処分品として安く販売されることが多いのです。
このため、10月頃に価格をチェックするとお得なテレビを見つけることができるかもしれません。
ただし、メーカーによって新製品の発売時期は異なる場合があるので注意が必要です。
また、在庫処分は現品限りであるため、必ずしも欲しい商品があるとは限りません。特に一品限りで安くなっている場合は、早い者勝ちです。
このため、「安いものが見つかったらラッキー」と思って見ることをお勧めします。
他の狙い目
さらに、店舗の閉店セールも見逃せません。閉店セールは不定期ですが、在庫を処分する必要があるため大幅な値引きが期待できます。常に情報をアンテナを張り巡らせて、閉店セールの看板を見つけたらぜひ足を運んでみてください。
私の知り合いは、15万円の洗濯機を7万円で購入しました。これは半額以下で手に入れた例です。
最適な購入タイミング
さて、テレビの買い時についてですが、やはり6月〜7月をお勧めします。この時期はテレビの価格が最も低くなるため、積極的に狙っていくべきです。
最も安い時期に購入できれば、節約したお金を他の家電や趣味に使うことができます。
とはいえ、すぐにテレビが欲しい方や待てない方は、他のセール時期を狙うか、「テレビを安く買う方法」を試してみてください。
さらに、「どこでテレビを買うか」も重要です。最もお得に購入できる場所を知っておけば、1万円以上安く買うことができます。
いつでもテレビを安く買う方法
テレビが最も安い時期が分かっていても、故障などで「今すぐ欲しい!」と思うこともありますよね?そんな時に役立つ方法をご紹介します。
特定の時期でなくても、以下を読むことで、お得にテレビを購入できる可能性があります。
「テレビを買うならどこが安い?ネットと店舗の違いを比較解説!」を読んで、お得に購入してみてくださいね。
スマホ決済サービスを活用する
最初におすすめするのは、スマホ決済サービスの利用です。特にPayPay(ペイペイ)は、キャンペーン期間中に利用すると、支払い金額の最大20%が還元されます。
「存在は知っているけれど、使い方がわからなくて面倒」と思っている方は、ぜひ挑戦してみてください。高価なテレビを購入する際に20%の還元を受けられるのは大きなメリットです。
PayPayの利用はとても簡単です:
アプリを開いて登録
銀行口座またはクレジットカードからチャージ
店員にアプリを見せて決済
この4ステップで利用できます。PayPayを利用できる店舗も増えており、「エディオン、ケーズデンキ、ノジマ、ビックカメラ、コジマ、ヤマダ電機、ベスト電器」など、多くの家電量販店で使えます。
さらに、「スーパーやコンビニ、飲食店」でも使用可能です。
スマホ決済サービスは手軽に利用できるので、まずはアプリを登録してみましょう。
これらの方法を組み合わせることで、いつでもお得にテレビを手に入れることができます。
値引き交渉のすすめ
家電を購入する際の基本は「値引き交渉」です。普段は値引き交渉をしない人でも、家電を買うときはぜひ挑戦してみてください。
特に、展示品や在庫限りの型落ち製品は交渉がしやすいです。店舗としても在庫を抱えるより、売り切ったほうが利益になるため、意外とすんなり応じてくれることが多いです。
家電量販店に知り合いがいれば、さらにお得に購入できる可能性もあります。恥ずかしがらずに声をかけてみましょう。実際、多くの販売員さんは積極的に値引き交渉に応じてくれます。
値引き交渉をためらう方もいますが、家電の購入時には普通のことなので、積極的に交渉してみてください。値引きのコツをつかんで、賢く買い物をしましょう。
インターネットで購入する
家電量販店に行かなくても、インターネットで簡単に家電を購入できる時代です。多くの家電はオンラインでも購入可能で、場合によってはインターネットの方が安いこともあります。
「楽天」や「Amazon」、「Yahooショッピング」などでお得なテレビを見つけることができます。東芝やパナソニックなどの有名メーカーの新品テレビもオンラインで購入可能です。
ただし、インターネットで購入する際は、配送料がかかる場合やサイズ確認が必要です。私も以前、電子レンジを購入した際にサイズを間違えて返品した経験があります。
ジェネリック家電の利用
アイリスオーヤマなどの低価格ブランドも検討してみてはいかがでしょうか。最近では「ジェネリック家電」と呼ばれ、低価格でありながら必要な機能を備えた製品が人気です。
テレビもさまざまなブランドから販売されており、非常に安価なものもあります。基本的な機能だけで十分という方には、ジェネリック家電がおすすめです。
当サイトでは、「ジェネリック家電テレビのおすすめ」も紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
アウトレット家電
次に紹介するのは「アウトレット家電」です。大型家電量販店では、「アウトレット商品」を取り扱っている店舗もあります。
これらの商品は在庫処分品や生産終了モデルなどで、新製品や新品にこだわらない方におすすめです。
近くに大型家電量販店がない方でも、ヤマダ電機の公式オンラインショップ「ヤマダモール」でアウトレット商品を購入できます。
家電製品が非常に安い
ネットでも価格交渉が可能
ポイント還元が基本10%
サービス併用で最大12.5%まで可能
他店やネットの価格に対抗する企業方針
ヤマダ電機で家電を購入すると、底値で手に入れることが多いです。まずはヤマダ電機のショッピングサイトで価格を確認して、商品の相場を把握してみましょう。
アウトレット家電は基本的に中古品です。そのため、故障が発生する場合もありますが、保証に入っていれば安心です。
保証外の修理は新品の価格と同等になることがあるため、アウトレット品を購入する際には、保証に入ることをおすすめします。
古いテレビを買い取ってもらう
今使っているテレビの処分方法を決めていますか?家電量販店での引き取りを考えている方も多いでしょうが、実はもっと高額で買い取ってもらう方法があります。
日本最大級のリユースプラットフォーム「【おいくら】」では、不要な品物を一括査定してくれます。
スマホから簡単に見積もりができ、査定は約3分で無料です。価格に納得できない場合は断ることも可能です。
例えば、私の場合、5年間使用した冷蔵庫を1万円で買い取ってもらいました。
家電量販店では2,000円の査定だったので、5倍の価格で売れました。
このように、家電量販店の下取りよりも高価で買い取ってもらえるので、とても便利です。
家電レンタルを考える
最後に紹介するのは「家電のレンタル」です。一年間だけの単身赴任や一人暮らしの学生にとって、購入よりもレンタルが賢明な選択となる場合があります。
特にテレビのような大型家電は、引越し時に扱うのが大変です。しかし、レンタルなら解約するだけで済み、引越し時にはレンタル業者が運んでくれるので手間がかかりません。
テレビをレンタルできるサービスには次のようなものがあります。
DMMいろいろレンタル
モノカリ
かして!どっとこむ
テレビを必要とする期間が限定されている方には、これらのサービスをチェックすることをおすすめします。購入よりも低コストでテレビを利用できます。
テレビの寿命について
次に、テレビの寿命について説明します。平均寿命は8~10年程度です。意外に短いと感じるかもしれませんが、これは一般的な期間です。
テレビは高価な家電ですが、10年しか持たないと聞くと不安になる方もいるでしょう。しかし、壊れていないからといって10年以上使用するのは得策ではありません。
万が一壊れた場合、修理費が高くつくことがありますし、新しいテレビを購入するタイミングが悪いと、高値で購入する羽目になります。さらに、一度壊れた家電は再び故障する可能性が高いです。
壊れる心配をしながら古いテレビを使うよりも、保証のついた新製品を安い時期に購入する方が安心です。
テレビの寿命が近いサイン
テレビが寿命を迎える際に見られるサインを紹介します。現在お使いのテレビに以下の症状が見られる場合、買い替えを検討することをおすすめします:
異音がする
電源が不安定
これらのサインが現れたら、早めに新しいテレビを検討しましょう。
電源が入らない
テレビの電源が入らなくなるという症状はよくあります。たまに正常に映るからといって安心せずに、早めに対処しましょう。
電源基盤や回路の故障が原因で、突然電源が入らなくなることが多いです。
修理を考える方もいますが、古いテレビほど修理代が高くなるため、長く使っている場合は買い替えを検討する方が良いです。
映像の色がおかしい
映像の色が変になる場合は、本体の故障が原因です。この場合も修理代が高くつくことが多いため、買い替えをおすすめします。
ただし、電源を入れ直したり、コンセントを抜き差ししてみると一時的に治ることもあるので試してみる価値はあります。しかし、色の変化が続くようであれば、買い替え時です。
安全な新製品に買い替えましょう。
リモコンが効かない
テレビ本体が正常でも、リモコンが故障することもあります。
リモコンが使えない場合は、メーカーからリモコンを購入する必要がありますが、意外と高価です。
テレビを購入して1~2年であればリモコンの購入も一つの手ですが、5年以上経過している場合は、思い切って本体ごと買い替える方が良いでしょう。
リモコンを買った直後に本体が壊れることもあるので、買い替えた方が結果的にお得になることが多いです。安い時期を見計らって新しいテレビを手に入れましょう。
テレビの寿命を延ばす方法
テレビは高価な買い物なので、できるだけ長く使いたいですよね。
10年使いたいと思っている方も多いでしょう。実は、テレビの寿命を延ばすためのコツがいくつかあります。
ほこりを溜めない
テレビにほこりが溜まらないようにしましょう。ほこりが溜まると火災の原因になることもありますし、小さな部品にダメージを与え、故障の原因になります。
頻繁に掃除をして、ほこりが溜まらないようにしましょう。綿棒などを使うと細かい部分もきれいにできておすすめです。
寝る前に必ず電源をオフにする
テレビの部品には寿命があります。その寿命を大切にすることが、テレビを長持ちさせる秘訣です。
寝る前にテレビを見ていて寝落ちしてしまうことがあるかもしれませんが、見ていないのに朝までつけっぱなしにしておくと、電気代が無駄になるだけでなく、寿命も縮んでしまいます。
寝る前にテレビを見るときは、タイマー機能を活用しましょう。
使用時間を制限する
テレビの寿命を延ばすためには、使用時間を減らすことが効果的です。最も早く寿命が来る部品は8~10年が限界と言われています。
1日に使う時間を決めたり、見ていないときにはテレビを消すように心がけましょう。
私も見ていないのにテレビをつけっぱなしにしてしまうことが多いですが、これを避けることで寿命を延ばすことができます。
まとめ
テレビを購入する際は、家電量販店のセールを狙いましょう。
少しでも安く購入できれば、その浮いたお金を他の趣味や家族に使うことができます。収入をすぐに増やすことは難しいかもしれませんが、出費を減らすことはすぐにでもできます。
ぜひ、これらの方法を実践して、お得にテレビを購入し、長く使い続けてください。